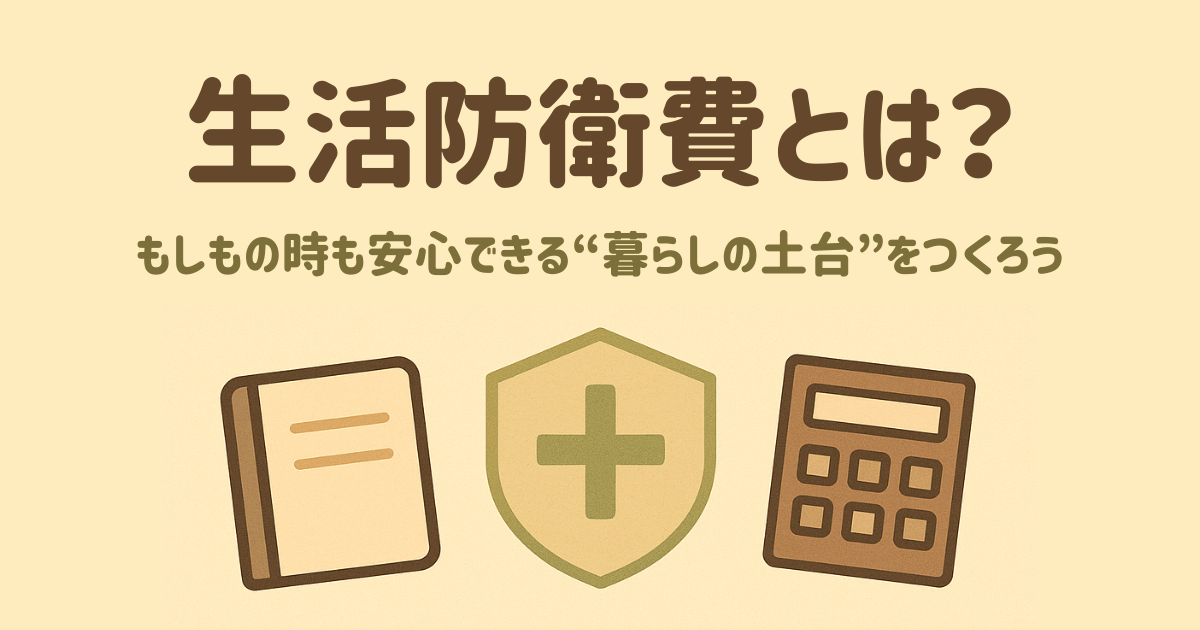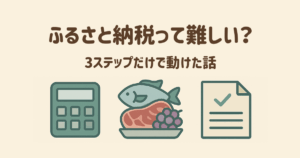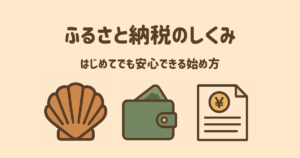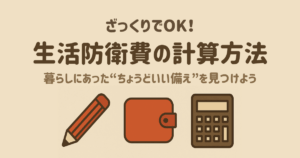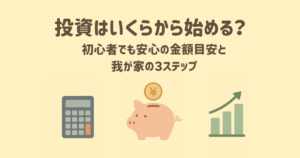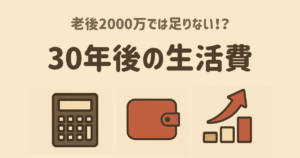みなさん、「生活防衛費」という言葉、聞いたことはありますか?
私は投資の勉強を始めるまで、この言葉を知りませんでした。
でも、知ってみると「これってすごく大事だな」と思うお金なんです。
生活防衛費とは、万が一のときに生活を守るためのお金です。
なぜ生活防衛費が大切なのか
たとえば…
- 仕事を辞めざるを得なくなったとき
- 病気やケガで働けなくなったとき
- 災害などで収入が止まってしまったとき
こうした“不測の事態”でも、しばらくの間は生活できるように備えておくお金が生活防衛費です。
生活防衛費はいくら必要?簡単な計算方法
基本の計算式
必要な金額は人によって違いますが、基本の計算はとてもシンプルです。
生活防衛費 = 1か月の生活費 × 備えたい月数
生活防衛費の計算例
たとえば、
- 月々の生活費が30万円
- 6か月分を準備したい場合
30万円 × 6か月 = 180万円
この180万円が、生活防衛費の目安になります。
生活防衛費の目安は何か月分?
一般的な目安(3〜6か月分)
よく言われるのは3〜6か月分です。
6か月分が安心とされる理由
もし急にお仕事を失った場合、失業給付金を受け取れる期間は90日〜360日ほどです(※1)。
ただし、自己都合で退職した場合は、最初の給付金を受け取るまでに約1か月半かかります(※2)。
さらに、失業手当の金額は、普段の収入の50〜80%程度。
また、病気やけがで働けなくなった場合は、健康保険から傷病手当金を受け取れることがあります。
支給期間は最長1年6か月ですが、金額は給与の満額ではなく、標準報酬日額の3分の2程度です。
いずれの場合も家計のすべてをまかなうには少し心配ですよね。
だからこそ、生活費6か月分を備えておくと安心です。
※1 離職理由や雇用保険の加入期間によって異なります。
※2 待機期間(7日間)+給付制限期間(1ヶ月)
状況別の目安(子育て・持病・収入の安定度)
- 子育て中
- 持病がある
- 収入が不安定
こうした場合は、1年分以上を備えておくとさらに安心です。
生活費に含める項目
必要な生活費の例
生活防衛費を考えるときは、まず毎月の生活費を把握することが大切です。
一般的にはこんな項目があります。
- 住居費(家賃・住宅ローン)
- 食費
- 光熱費
- 通信費(スマホ・ネット)
- 保険料(生命・医療など)
- 教育費(お子さんがいる場合)
- 医療費(通院・薬代など)
- 日用品費
- 交通費(ガソリン・公共交通など)
- 娯楽費
見直しや調整のポイント
娯楽費などは、収入が止まった場合には減らすことも考えて、必要最低限の金額を出すのがおすすめです。
まとめ|生活防衛費は“安心の土台”
今回は「生活防衛費ってなに?」という基本のお話をしました。
生活防衛費は、特別なお金ではなく、「安心して暮らすための土台」です。
まずは、自分や家族にとっての必要な生活費を知ることから始めてみてください。
次の記事では、この生活費をもとにした具体的な計算方法をお伝えします。
参考文献
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/002176733.pdf
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139