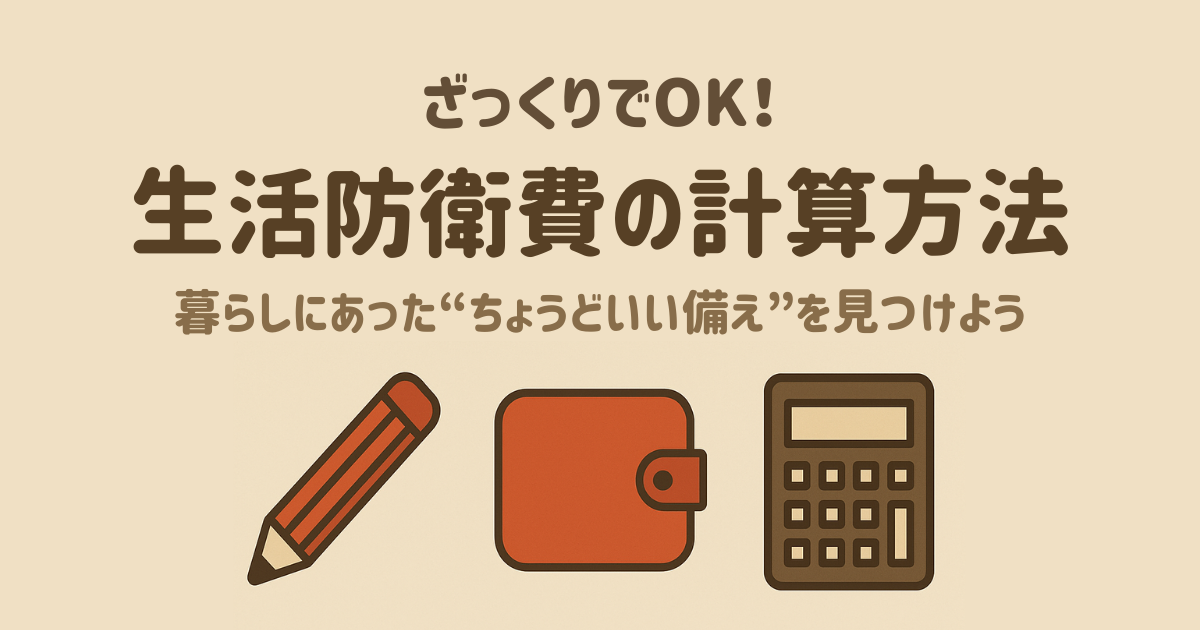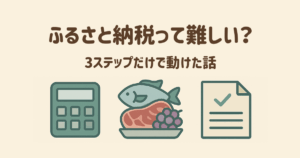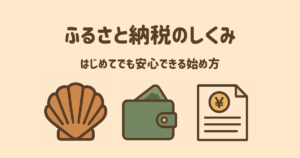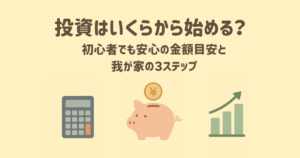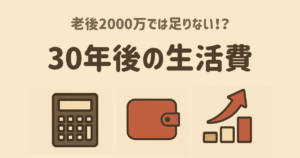生活防衛費は、「安心して暮らすための備え」です。
でも、実際にいくら必要かを考えようとすると、意外と迷ってしまいませんか?
私も最初は、どこから計算すればいいのか分からず、手が止まっていました。
でも今は、「ざっくりでいい」と思っています。
なぜなら、備える目的は“完璧な数字”を出すことではなく、
“いざというときに安心できる状態”をつくることだからです。
だから私は、生活防衛費を考えるときの支出を「生活費」と「特別費」の2つに分けて、シンプルに考えています。
生活防衛費とは、リストラや病気など、もしもの事態に備えておくお金のことです。
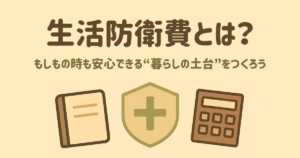
支出は「生活費」と「特別費」に分ける
生活費(毎月かかるお金)
毎月ほぼ同じように発生する支出です。
人によって内容は異なりますが、一般的には次のような項目があります。
- 食費:食材・外食・カフェ代など
- 日用品費:洗剤・トイレットペーパー・シャンプーなど
- 交通費:ガソリン・電車・バス・タクシーなど
- 被服美容費:洋服・美容院・化粧品など
- 医療費:通院・薬・健康診断など
- 交際費:飲食・ご祝儀・香典など
- 住居費:家賃・住宅ローン・管理費・駐車場など
- 通信費:スマホ・インターネット・固定電話など
- 水道光熱費:電気・ガス・水道
- 保険料(月払い分):生命・医療・自動車・火災保険など
- サブスクリプション:動画・音楽配信、新聞、ジムなど
特別費(年に数回だけ発生するお金)
普段は発生しませんが、年に数回まとまって必要になるお金です。
どのくらい、どんな項目があるかは、家族構成や生活スタイルによってさまざまです。
税金:自動車税・固定資産税・住民税(一括払い)など
- 保険料:生命保険・火災保険・自動車保険など
- 帰省・旅行費:お盆・年末年始の帰省、家族旅行など
- イベント費:クリスマス・誕生日・お年玉・お歳暮・お中元など
- 教育費:入学金・授業料・修学旅行・塾の特別講習など
- 車両費:車検・タイヤ交換・定期メンテナンスなど
- 家電・家具購入費:冷蔵庫・エアコンなど高額品の買い替え
生活費も特別費も金額は、家族構成や地域、持ち家か賃貸かなどによって大きく変わります。
生活防衛費の計算式と具体例
ここまでで生活費と特別費の内訳を見てきました。
では、実際に生活防衛費を計算してみましょう。
一般的な生活防衛費の計算方法
一般的な計算方法は、非常にシンプルです。
生活防衛費 = 1か月の生活費 × 備えたい月数
たとえば、1か月の生活費が30万円で、6か月分備えたい場合は、180万円が目安となります。
ちょっと多めが安心|心配性LANA.の生活防衛費の出し方
私は、より安心できる金額を出すために、生活費に加えて特別費も少し含めて計算しています。
そうすることで、急な出費があっても心がすり減りにくくなると思っています。
生活防衛費 =( 生活費の月額 × 備えたい月数 ) +( 特別費の年間額 ÷ 4 )
この計算方法では、毎月の生活費に加えて、車検や税金といった「特別費の年間額」の1/4も生活防衛費に含めます。
1/4にする理由は、「いざ」という時に備えながらも、貯める負担を軽くするためです。
もちろん、年間特別費を全額や1/2まで備えられれば、安心度はさらに高まります。
でも、まるごと用意しようとすると、途中でしんどくなってしまうこともありますよね。
だからこそ、ゼロではなく1/4だけでも確保しておくことで、「とりあえずこれだけあれば」という安心感につながります。
具体例
- 1か月の生活費:30万円
- 年間の特別費:72万円
この場合、特別費の1/4は18万円です(72万円 ÷ 4)。
- 6か月分備える場合 (30万円 × 6か月) + 18万円 = 198万円
- 1年分備える場合 (30万円 × 12か月) + 18万円 = 372万円
このくらいが、私にとっての「備えすぎず、足りなすぎず」のちょうどいいバランスだと感じています。
備えたい月数は安心できるラインで決める
私は6か月分あれば安心かな、と思っています。
でも、これは人それぞれです。
お子さんがいたり、持病があったり、収入が不安定だったりする場合は、1年分以上あると安心かもしれません。
逆に、夫婦二人暮らしで会社の保障が整っているなら、3か月でも十分なこともあります。
大事なのは、自分が「これなら安心できる」と思えるラインを見つけることです。
最後に|数字が苦手でも「ざっくり」でいい
今回は生活防衛費を考えることが目的なので、支出項目はあえてシンプルにしました。
本格的に家計を見直すときは、また別の記事でお話ししますね。
生活費の全体像をつかむうえで大切なのは、
「何にどれくらい使っているか」をだいたい知っていること。
きっちりでなくても、ざっくりでも。
自分で把握できていれば、それだけで立派な備えです。
備えることは、こわい未来を想像することではなく、安心して“いま”を暮らすための準備。
それが“ちょうどいい備え”となります。