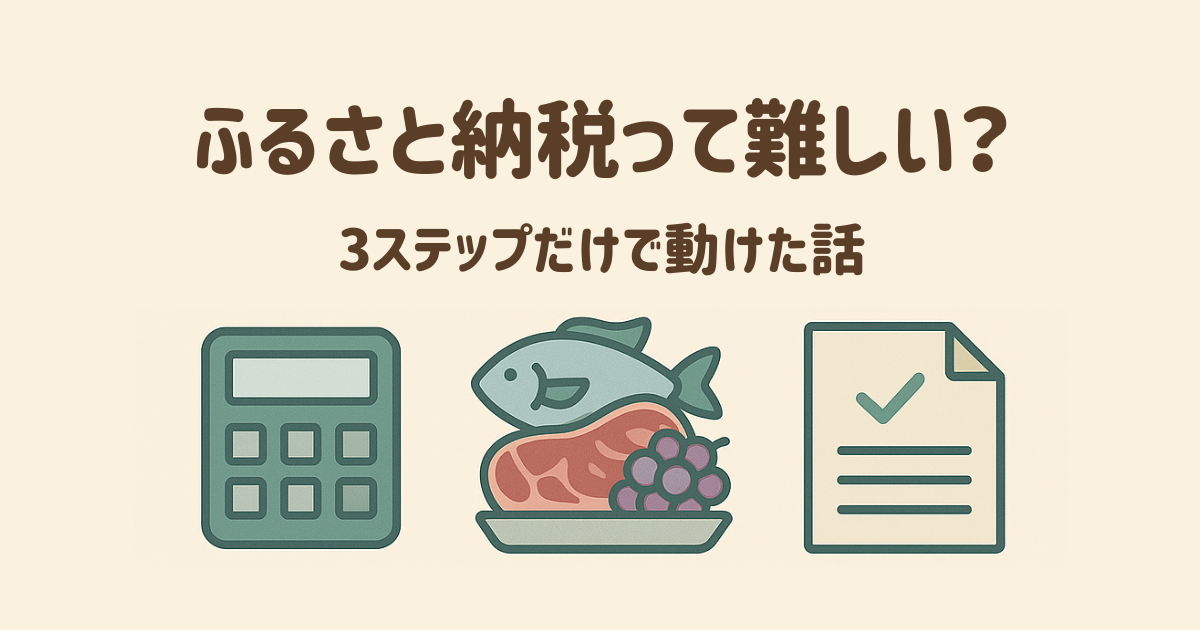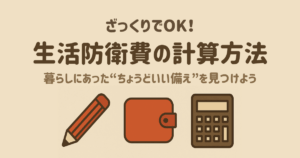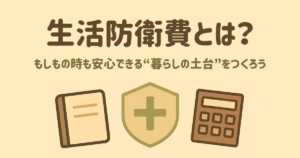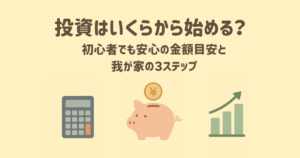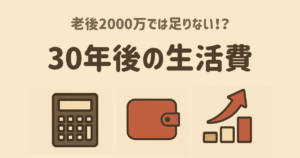「ふるさと納税、やったほうがいいよ」
そう聞くたびに気にはなっていたけれど、なんとなく難しそうで手をつけられずにいました。
控除?手続き?
よくわからないまま、つい後回しにしてしまって…。
※「仕組みをもう少し知りたい」という方は、こちらの記事もどうぞ。
でも実は、「上限を知る → 選ぶ → 手続きする」
この3ステップだけで進められるとわかってからは、一気にハードルが下がって。
去年ようやく、私もはじめて寄附できました!
STEP1|“ざっくり上限”を知る
ふるさと納税には「上限」があります。
年収や家族構成によって、“ここまでなら控除される”というラインがあるんです。
ただ、そこを1円単位で正確に出す必要はありません。
多くの人は、ポータルサイトの「簡易シミュレーター」でざっくりした目安を出して、それを基準にしています。
私も、そこで「たぶん4万円くらいかな」と出たけれど、実際にはその1万円下くらいまでにしています。
上限を超えてしまうと、控除されずに“そのまま寄附扱い”になってしまうので、私は「ちょっと余裕をもたせておく」ほうが安心なんです。
もちろん、上限ギリギリまで寄附するのもOK。
ご自身の安心できる範囲で選んで大丈夫。
📌 やること:
ふるさとチョイスのシミュレーターで上限を確認
→ 出た金額から1万円引いた額を“実際の上限”としてメモ
📝 例:心配性な方は、目安は4万円 → 寄附は3万円くらいまでにしておく
STEP2|“寄付先”を選ぶ
上限の目安がわかったら、あとはその範囲で、どこに寄附するかを決めます。
私は「生活でちゃんと使えるもの」を基準にすることが多くて、毎日使うトイレットペーパーや、大好きな波佐見焼のお皿を頼んだこともあります。
ときどき、ちょっと特別な果物を見てみたり、地元の自治体をのぞいてみたりもします。
応援したい地域でもいいし、返礼品で選んでもいい。
選び方って、人それぞれでいいと思います。
「ふるさと納税だから特別なことをしなきゃ」と思わなくても、
いつもの延長で選ぶだけで、ちょうどいい気が私はしています。
📝 ただひとつだけ意識しているのは、「5自治体以内にすること」。
理由は、次のSTEPで出てくる「ワンストップ特例」という手続きを使うためです。
※ 同じ自治体に複数回寄附しても、“1自治体”としてカウントされます。
STEP3|手続きは「ワンストップ」か「確定申告」
寄附したあとは、手続きを忘れずに。
やることはどちらか1つだけです。
A)ワンストップ特例
- 対象:確定申告をしない人(会社員)で寄附先が5自治体以内
- 内容:寄附後に届く申請書+マイナンバー確認書類を送るだけ
- 締切:翌年1月10日必着
- 控除:翌年6月〜翌々年5月まで、住民税が毎月少しずつ減る
- ふるさと納税サイトによっては、購入履歴ページから「ワンストップ特例申請」ができる場合もあります。
- マイナンバーカードが必要で、対応自治体のみ対象です。詳しくはふるさと納税サイトをご確認ください。
B)確定申告
- 対象:医療費控除や副業収入がある人など確定申告をしている人
寄附先が6自治体以上の人 - 内容:寄附先から届く証明書を、確定申告で提出
- 締切:翌年3月15日まで
- 控除:所得税は1〜2か月後に還付、住民税は6月から減額
実感メモ|いつ“安くなった”と感じる?
私の場合、「ほんとに税金減ったの?」と半信半疑でした。
でも、翌年6月の住民税通知書で、毎月少しずつ引かれる額が減っているのを見て、
ちょっと嬉しかったです。
🕒 タイミングの目安:
| 手続き方法 | 控除の実感タイミング |
| ワンストップ特例 | 翌年6月〜翌々年5月、住民税が12回に分けて減額 |
| 確定申告 | 所得税:申告後1〜2か月で還付 住民税:翌年6月から減額開始 |
今日やること3行まとめ
- 上限をざっくり調べて、少し控えめの金額をメモ
- 返礼品などから、寄附先を選ぶ
- ワンストップ or 確定申告を決めて、締切(1/10 or 3/15)をカレンダー登録
ふるさと納税の仕組みを知りたい方は、以下の記事もどうぞ!
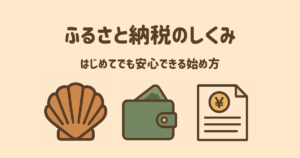
補足メモ
※ わかりやすさのため「税金が安くなる」と表現していますが、
正式には「所得税・住民税からの控除(寄附金控除)」です。
制度の定義・計算方法については国税庁の案内をご確認ください。